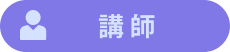コラム
人事コラム:賃上げブームの舞台裏
企業は賃上げにどう対応したらよいのか?
コラム記事
2024/04/22
近年の物価上昇と人手不足を背景に、2023年より一気に潮目が変わり、ここ30年で最高の賃上げ率となりました。ベースアップも多くの企業が実施しています。この流れは一過性のことではなく、しばらくは賃上げムードは続いていくと予想されます。しかしながら、この賃上げによる人件費の増加にいつまでも耐えうる企業ばかりかというとそうではありません。人件費全体を単に増やしていくのが難しくなる局面に今から備えていく必要があります。
このコラムでは、3回に分けて、昨今の賃上げブームの背景と企業が賃上げにどのように対応したらよいかについて、解説していきます。
1.近年の賃上げ動向と今後の予測
2.企業は賃上げにどう対応したらよいのか?(本コラム)
3.賃上げに関する質問に答えます
今回は、企業が賃上げに対応しつつ、経営を圧迫しないように人件費の重点配分や効率的な支払いなども実現していく手段についてお伝えします。
企業は賃上げにどう対応すべきか?
まずは単純な計算で、高水準の賃上げを続けることは可能か考えてみましょう。例えば、5%の昇給をし続けると15年後には給与はおよそ倍、7%昇給では2.5倍となります。昔の昇給率は大体2%ぐらいが平均とすると、初任給22万円スタートで勤続15年でも29万円、3割ほどしか上がりません。確かに日本の給料は上がっていないと言えます。これが昇給率5%になると結構状況も変わってきて、15年後には43万円、およそ2倍になります。
「海外の会社では給与が倍になっている」という表現も見かけますが、実は当たり前のことです。海外(特にアジア圏)では「毎年1割ずつ上げていこう」というような国の政策があり、日本より昇給率が高く、短い期間で給与が倍になります。これができれば会社としても国としても良いのでしょうが、まだなかなか難しいです。
確かに多くの会社がどんどん給与を上げています。短期的には世間の流れに対応することも重要ですが、中長期的な企業の継続性や重視したい人材の獲得、リテンションを考慮した人件費の支払い方の最適化など、報酬制度全体の見直しも視野に入れる必要があります。「そもそも、うちの会社はこれ以上賃上げする必要があるのか?」という検討も必要です。
賃上げに対する企業の対応は、現実的には以下のような対応が考えられます。
1.自社の報酬水準について把握する
同業界や同地域内の他社と比べて、元々給与水準が高い会社もあります。そういう会社で従業員にヒアリングしてみると「不満は給与ではなく○○です」という話が出てくることもあります。給与水準が低い水準であればせめて世間並みに引き上げるとか、優秀な層は特に引き上げるなどの施策が考えられますが、給与水準が高い水準であれば自然と賃上げの優先度は下がります。
2.人件費の支払い余力について確認する
人件費の支払い余力を考えずに、支払える・支払えない議論をしていることがよくあるようです。今の利益構造の中でこれ以上人件費を増やせる余地があるのか、余地がなければどうするかの議論が必要です。人件費を増やせる余地がなければ、人件費の再配分(引き上げ部分を重点化)を考えていきましょう。
3.自社の人件費支払い傾向を確認する
上記2.を実施するためにも、人件費を重視したい人材層に手厚く支払えているか、逆の人材層に多く支払いすぎていないかのチェックが大切です。「当社は年功序列です」と言う会社をよくよく見るとそうでもなかったり、「当社は実力主義です」と言われてよく見てみると実は年功序列だったり、そういったことが結構あります。例えば後者のように、実力主義と言いながら実態は年功序列だった場合には、年齢だけ・勤続年数だけで上がってしまった人件費をどうするかの問題が出てきます。また、手当に関しても、制度導入時には意義があったのに現在は既得権化しているだけの手当がないか、確認が必要です。
4.人件費の配分見直しを考える
1~3を踏まえて、重点的に採用・リテンションしたいターゲットはどのような人材かを明確にしましょう。年齢構成も重要なポイントです。給与カーブを見直しして、人件費配分にメリハリをつけていきます。
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.自社の報酬水準について把握する
目的に応じて情報のソースが異なります。
産業別・職種別の相場を調べる場合
賃金構造基本統計調査
厚生労働省が統計を取っており、1番調査対象母数が多いため、信頼度は高いと言えます。メリットは母数が多いこと、切り口が多いことです。男女別・学歴別・都道府県別・年齢別等、多くの切り口があります。デメリットとしては産業の分類が古い・粗いことです(統計全般に言えることですが…)。例えば情報通信業といっても、その中に給与水準が低い・高い、水準が異なる企業がありますが、それらを混ぜて同じ業種としていたりします。産業分類が時代に即したものになればより分かりやすくなると思います。
求人サイトの平均募集額
より詳細な職種で平均額が掲載されており、実際に存在する金額を集計しているため、一定の信頼度があります。昔はあまり参考にしませんでしたが、最近は「同じ職種でどれくらいの金額幅で募集をしているか」などを見ています。ただ、やはり入口でしかない(採用統計でしかない)ので、他データと組み合わせて調べましょう。
個別企業の水準を調べる場合
平均年間給与(有価証券報告書)
上場企業に限られますが、平均年齢と平均年間給与を確認できます。ただし統一ルールがあるわけではないので、何をもって年間平均給与としているか、集計対象が明確ではありません。会社によって正規雇用の平均値だったり非正規雇用も含まれたりと、どこまで使えるかには注意が必要です。
口コミサイト
転職者や退職者が自らの意思と経験に基づき書き込んだ情報なので、信頼性はそこまで高くありません。残業代など、どのような給与項目を含めて書き込んでいるかは各自の判断が大きく影響します。昔は見なかった情報源ですが、最近は見る意義があると思っています。転職者や新卒者も結局「これが正しいのだろう」と見ているので、押さえておく必要はあるでしょう。
調査会社に依頼
費用が掛かるいわば裏技ですが、調査会社に依頼すると給与・賞与水準や項目に関する詳細な情報が入手できます。調査会社に依頼しなくても、例えばお付き合いのある人材紹介会社から情報収集する地道な方法もあります。
自社の報酬水準について把握する(事例)
年収(年齢別)の水準について統計と自社の比較をしてみましょう。例えば横軸が年齢で縦軸を年収とし、業界の統計値が青で自社が赤とします。
こうして並べてみると、年収は30歳代後半まで、統計値のほうが高いかほぼ同等の水準にあることが分かります。40歳代以降と全体では、自社のほうが高い水準にあります。40歳以上は十分な水準が確保できているため、若年層の引き上げに注力しようと判断できるわけです。
また、競合他社の有価証券報告書の財務内容や平均給与から比較表をつくり、他社が利益のうちどの程度を人件費としているかを確認してみましょう。この表で見ると、平均年齢40歳で平均年収1,200万円の会社もあれば、43歳で878万円の会社もある、と比較できます。先ほど「いろいろな情報が混じっていてあまり当てにならない時もある」と述べましたが、大体社名のイメージ通りの結果が出てくることが多いです。これで何が分かるかというと、「当社は平均年収が高い、しかし平均年齢もまた高い」可能性を発見できます。一方で「平均年齢が低いのに平均年収は高い」となると、本当に給与水準が高いと分かります。
上場企業ではなくても情報を集める意義はあります。例えば上場していないオーナー企業でも、上場企業レベルの人材をターゲットに考えたい場合です。採用に応募する側は「上場企業の方がいい!」というイメージを持っているのに対して、非上場企業でも「当社は上場企業並みの水準ですよ」と具体的にアピールできます。
ポイントは賃金だけとは限りません。例えば「給与は高いが労働時間が長い」となると、給与以外の問題が出てきます。年間休日数の世間相場が120日程度に対して自社は113日で少ないとか、賞与も定期昇給も少ないとなると、それらを世間並にする必要があります。このような処遇や労働条件は、個別に比較しないと分かりにくいものです。報酬水準は高くても、全般的に見るとよろしくない状況、ということもあり得ます。
参考:ベースアップと定期昇給
ベースアップとは賃金カーブの是正です。ベースアップは賃金カーブ全体を引き上げること(実務的には賃金表全体を増額させること)です。近年の主流は全社員の賃金水準を一律に上げるのではなく、若年層の引き上げ額を高くして、それ以外の層をある程度抑える形になっています。
本来の趣旨は物価上昇への対応です。デフレ下でも実施されてきたのは、賃上げを目的とした政府主導の官製ベアと呼ばれています。連合は「2024年春季生活闘争方針」にて、ベースアップ+定期昇給で賃上げ5%以上を求めるとしており、対する経団連も「賃上げは社会的責務」として前向きな姿勢を示しています。
2.人件費の支払い余力について確認する
人件費の支払い余力の確認方法にはいろいろな方法がありますが、当社では基本的な考え方としては「労働分配率に基づく」としています。労働分配率は総額人件費÷付加価値額で算出されます。会社が稼いだ額(付加価値)に対して、どれだけの人件費を払っているかを表す指標です。付加価値額の算出方法には控除法と加算法があり、大体は加算法を使います。しかし、正直に言うと、付加価値額を算出するのはなかなか面倒です。そのため、以下の方法で確認していることが多いです。
それは、会社が大事にしたい指標(大体は営業利益か経常利益)に対して、人件費総額がどれだけの割合を占めているかを経年で見ていく方法です。ポイントは経年です。統計と比較して、例えば黄色の折れ線グラフとオレンジの棒グラフが製造業の業界平均、赤い折れ線グラフと青い棒グラフが自社とします。統計(黄色)よりも自社(赤)の年収総額比率が低いとはどういうことかと言うと、よく言えば「人件費効率が良い」ですが、悪く言えば「あまり人件費に充てていない」となります。営業利益に対する年収比率が統計よりも低い水準にあり、経年でも横ばい=支払い余力はある状態です。統計だけの比較ではいろいろな業種が混じってしまうので、経年で見ることが大切です。
例えば、これまで通りの運営を続けて、赤線(人件費比率)がどんどん下がっている会社は当然利益が上がっているので、数年後も大丈夫そうだから人件費を上げよう、という判断ができます。逆に、赤線(人件費比率)がどんどん上がっていたら、人件費を上げるのはなかなか厳しいかもしれません。こういったことが見えてくるので、経年での統計比較をお勧めします。
もう少し余力があれば、将来予測もやってみましょう。将来の人員数の増加と昇給率を加味して、人件費の予測値を出し、支払い余力を検証します。
例えば、平均年収600万円の人が毎年10人増えると仮定し、社会保険料や昇給率(3~5%など)を見込んで、今の利益がずっと継続するのか、0.5%ずつ増えていくのかを10年分シミュレーションします。すると確かに赤い線(自社の営業利益に対する年収総額比率)は右肩上がりですが6割ほどで、一つ前の図で見た製造業の平均(黄色折れ線)は大体7割であり、自社はまだまだ支払い余力があると考えられます。こうしたシミュレーションによって、ある程度自社の支払い余力を知ることが可能です。
3.自社の人件費支払い傾向を確認する
自社の人件費支払い傾向の確認のために実施いただくとよいのは、給与等の分布を見ることです。大切なのは基本給と給与(基本給に諸手当や残業代を加算したもの)と年収を見ることです。よく年収だけを見る方がいますが、年収には賞与というファクターが混じって不正確になってしまいます。年収だけを見ると今の固定給への疑問に対応できなかったり、成績の良し悪しで賞与の支払いが変わったりしますのであまり当てになりません。基本給、給与、年収といった形でいくつかの切り口でプロットしましょう。
このグラフの会社は、とても中途採用が多いので基本給の額にばらつきがあり、年功序列とは言えない状態です。勤続年数が短くて基本給の高い人もいれば、勤続年数が長くても基本給の低い人もいます。これは中途採用する際に、言われるがままの給与水準で採用を続けた結果です。今後はある程度揃えて、毎年勤続していたらしっかり上がるようにしたいと考え、新しくモデルを組んでモデルからはみ出しすぎる方を補正した事例です。今後、新入社員が標準評価で昇給・昇格した際に逆転しないように、基本給が青線(新モデル)未満の方はモデルまで引き上げました。ただし、勤続年数が長いモデル未満の基本給の方については、評価で基本給が上がっていない方もいるので必要に応じて個別に調整となりました。
今度はもう少し揃っている例です。横軸が等級で右に行くほど等級が高くなりますが、支給額が高すぎる(点が上に飛び出している)方がます。これは昔から特殊な事情があって上がり続けてきた人のようですが、こういったところに人件費を充てているのもいかがなものかと話題になり、分布を作ってみたものです。分布を見ると、上げるべきところや上げなくていいところ、むしろ抑えた方がいいところなどいろいろなものが見えてきます。
あとは手当の見直しです。手当もいくつか見ていく軸があります。最初の段階では意義があったものの、世間相場を見て廃止されたり、社内で「不公平だ」と声が上がって廃止されたりした手当もあります。例えば最近よく言われるのが、家族手当自体は生活を支える意義があるとしても、扶養に入れている方だけに払う形だと男性ばかりに偏るという問題です。実際に集計してみると、男性受給率90%に対して女性受給率は10%(配偶者や子どもがいる方でも)です。
こんな不公平を見直していく、もしくは「当社はもう成果で払います」という場合にはなくしていくことも考えられます。食事手当がまだ残っている会社もありますが、残っている理由が「なんとなく昔からあるから」であれば廃止しましょう。一方で寒冷地手当ですが、以前に食事手当と同じ論法で廃止したらいきなり大寒波がやってきたなんてこともありました。
手当については、当初の意義、世間相場、不公平感について把握し、見直していくのがよいでしょう。その他、手当はその手当をもらった側が喜ぶことが前提のため、そうでないようでしたら見直していくことも必要でしょう。
参考
以下は当社で分析する時の大体のメニューです。
- 分析結果 サマリー:全般、制度分析、データ分析
- 人事制度分析 詳細:等級制度、評価制度、報酬制度、定年・再雇用
- データ分析 詳細:分析の前提、人員構成、給与・賞与構成、報酬分布、昇給、残業時間、評価結果、報酬比較、初任給、生産性分析
残業時間も結構影響があります。「給与が低いけれど残業が多いから年収ベースはものすごく高い」なんて会社もあります。しかし逆に言えば、残業しないと稼げないということなので、残業代の算定基礎が上がってしまいますが、働き方改革と合わせて残業を減らした分だけ給与に入れていくという考え方もあります。多角的に見ていくとよいでしょう。
4.人件費の配分見直しを考える
日本の賃金の基本的特徴
業界にもよりますが、日本の給与は基本的に右肩上がりです。勤続年数≒年齢により水準が上がります。厚生労働省のよくあるデータで横軸が年齢・縦軸が給与のグラフがあります。業界ごとに見てみると、例えば金融業だと右肩に上がって55歳辺りで下がり、一方で介護などサービス業ではほぼ横一直線でほとんど上がりません。大体世間のイメージ通りです。
また日本の企業の特徴として、実質的な賃金後払い(若い時は安く、中高年は高く)があります。勤続年数が短い・年齢が低い間は「後で返ってくるから今頑張れ」と言われ、その「後」に充てるものが手厚い退職金と言われていました。一般従業員でも一定水準の退職金が支給されることが多く、回収できるのが40歳後半からでしたが、だんだんこれも崩れてきています。
パフォーマンスに対して相応の給与を支払おうというジョブ型では、この図の通りにはなりません。40歳代以降の年齢の高い方が仕事の内容や評価によって給与の高低があったり、年齢の高い層の分の原資が若年層に回っていくように見直している会社も多いです。
人員構成
年齢分布も見ていただきたいところです。よく「当社は中高年で支えられています」という会社があります。その会社で1番活躍しているのが中高年で、なおかつ勤続によって習熟していく仕事である場合です。そういった会社で1番やってはいけないのは、中高年層の人件費を抑えて若年層に回すこと。1番活躍している中高年層が頑張って長く働いているのに若年層に回しても、若年層は中高年層より辞める可能性が高いのです。どんなに給与を頑張って高くしても、よそがもっと高かったらよそへ行ってしまう特性も否定できませんから、そう考えると中高年層を大切にする方が良いでしょう。
中高年層の給与を上げていくというよりは、「定年を伸ばそう、緩やかに昇給もしていこう」という考え方もあります。それでは新陳代謝していかないのではと言われますが、現実問題で足元を見て、すごい策をひねり出して若年層を採用しようとしても、そもそも人が集まらない場合には、やはり中高年層に目を向けていく必要があります。年齢構成と業界特性(勤続に応じて習熟等)によっては、昇給は緩やかにして、長く安定的に働ける体制の整備という選択肢もあるのです。
これは逆もしかりで、年齢もしくは勤続年数と習熟に関係がない業界であれば「中高年層に払いすぎだ」となってきますので、大手企業では早期退職を募るなどしています。それ以外でも、中高年層は実力がなければ役職にもつけないし、役職につけなければ給料も上がらない形にして、若年層に回していくという考え方もあります。
皆の給与が上がっていくのはいいことですが、息切れ対策を考えると、自社の状況を見て判断していくことが大事です。よく「給与カーブを右肩上がりからならしていきましょう」という話がありますが、自社の状況に応じて考えた方がいいでしょう。
役割の大きさと水準
業務負担や職責により処遇が変わるのが基本です。同一労働・同一賃金もこの考えに基づきます。あまりに給与格差をつけていくと時に裁判になることもあり、やりすぎると労務的に厳しい部分も出てきます。ただ基本的な考え方としては、やはり責任・役割が重いところには多く払って、そうでもないところにはそうでもない額、という均衡が大切です。賃金格差はあってもいいから、それに明確な理由を持つという均衡という考え方で考えていきましょう。
モデル見直し
これは極端な例ですが、評価があまりよくない人は給与もほとんど上がらない一方、活躍する人はどんどん給与を上げていくモデルです。これも向き不向きがあり、例えば建設業などでやると間違いなく難しいことになるでしょう。活躍とは何をもって活躍かが不明確だからです。
このグラフは営業会社のモデルで、営業は成績が見えやすいので活躍する人はどんどん給与を上げて、そうでない方はあまり上げないことに納得感があります。ちなみにこの会社の昇給率は低く、2%ぐらいです。その代わり活躍すればどんどん昇格させて給与をどんどん上げていきましょうと、こういう設計をしているわけです。
逆に製造業では、技能にある程度習熟すると、それ以降は役職についていなければ人件費を多くしてもしょうがない、という考え方の制度が多いです。ある会社の制度設計の事例ですが、一定の役割、ここでは係長に到達するまでは昇給していくのですが、係長より上にいかなければ昇給頭打ちとなります。一方で係長より上の役割に到達する方は昇給が続き、給与水準は現行の制度よりも上がります。この会社は自動車業界の会社です。今は自動車業界も厳しいので、「全員が給与が上がっていくモデルでは厳しい」ということで、給与を上げていく人・上げていかない人を分けていきましょうという考え方になっています。
キャリア別水準
ある会社ではキャリアパスのどこかで、キャリアが1回頭打ちになると給与も一定程度で止まりそれ以降上がらなくなります。ただ「一定程度で上がらなくなる」制度にも1つポイントがあります。この「一定程度」が生活できないレベルだと、どうしても従業員は辞めてしまいますし、先に述べた社会的責任についても問われてしまいます。ですから「一定程度」の水準はよく考えて設計していく必要があります。
賃金水準に関しては、連合がリビングウェイジというデータを算出しています。リビングウェイジとは「労働者が健康で文化的な生活ができ、労働力を再生産し社会的体裁を保持するために最低限必要な賃金水準(出所:https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/living_wage.html)」と定義されているもので、大体4人家族モデルが600~700万円ほどです。例えば勤続20年で600~700万円ほどで推移し、そこから先は役割によるという考え方の1つのモデルです。
年功抑制
最近は減ったように感じつつ、結構まだ見かけるのが年齢給・勤続給ですが、これは果たして良いものでしょうか。昔は一方的に上がっていく給与を年齢で是正していましたが、中途採用が入ってきた時にそれは崩れてしまいます。それならば最初から年功色を薄めるために年齢給・勤続給をなくして職能給に一本化した方がよいでしょう(ただし、昇格・昇給に積み上げ要素があるため、年功は一定程度維持されます)。
ジョブ型
人件費の再配分の最たるものはやはりジョブ型です。メンバーシップ型(いわゆる職能資格・年功序列)からジョブ型へ変更すると、給与カーブは「後払い」から「その時払い」に近くなります。安直に「ジョブ型は良いか悪いか」のような議論が進んでいる風潮はいかがなものかと思いますが、ジョブ型は再配分の考え方です。例えばメンバーシップ型では年齢とともに給与がどんどん上がっていきますが、それを職種でならそうとするのがジョブ型です。
たまに「ジョブ型はみんな給与が上がる」なんて文言を目にしますが、それはあり得ません。最初から給与が高い職種は高く、低い職種は低いのがジョブ型の基本だからです。給与はジョブ=職種によって決まり、モチベーション対策上ある程度昇給はしますが同じジョブである限り打ち止め、そんなモデルです。
これが向く職種と向かない職種があるので、自社はどうなのかをよく考えてみましょう。ざっくりしたイメージでは、どんどん中途採用している会社やIT業界はジョブ型向きと言えます。反対に建設や製造など、技能で給与がどんどん上がっていく業界にジョブ型は不向きで、無理に導入するとまずいことになるかもしれません。
報酬構成比
あとは「賞与が高く給与は低い」こういった考え方もあります。賞与が大きいことは会社側に大きなメリットがあり、変動の幅が大きいと業績が悪い時に年収を抑えられるということで、導入した会社が多いです。けれども実態を見ると、そういう会社に限って固定払いにしていて、「賞与は夏冬2ヶ月分ずつ必ず払っています」という形になっています。そのような会社であれば、もう基本給に賞与分を振り分けましょう。そうすると残業代も賞与の算定基礎も上がりますし、そこから賞与は変動要素を高めていく考え方もあります。
要は賞与(変動)の一部を給与(固定給)に振り分け、給与の安定感を持たせる一方で、賞与の変動部分を拡大するのです。この方法は導入した会社がいくつかあり、安定感をもたせたかったり、固定給志向の会社も多いのかなと思います。
変動分拡大
会社業績と個人評価の反映度を高めるため、賞与の生活保障分と業績連動分の配分を見直します。例えば製造業でよくある例ですが、現行の賞与が「生活保障分3.5か月(固定賞与)+業績連動分1.5か月(変動賞与)=年間5.0か月」のように、固定賞与の割合が高いということがあります。これを固定賞与分の一部を固定給に移行させ、代わりに変動分を大きくすることで、「生活保障分2.0か月(固定賞与)+業績連動分3.0か月(変動賞与・業績連動によって±100%変動)=年間5.0か月」とするパターンなどがあります。
まとめ
ポイントは「今年の昇給は想定内。去年に比べて高く、今後もそれが続いていく」ということです。これに対する対応としては、2つあり、1つは自社の状況を見て、自社にとってどういった人件費の配分がいいのかを考え直すことです。もう1つは支払い余力があればそれに応じて人件費を上げていくこと、余力がなければ再配分に目を向けていただくのがよいと思います。
もっと詳しく知りたい・相談したい方へ
「今考えていること・悩んでいることについて、外部からの意見がほしい」
「とりあえず何から始めたらいいかのヒントがほしい」
という企業向けに、壁打ちのディスカッションや1時間のオンライン無料相談も承っています。どうぞお気軽にご相談ください。
最新セミナー情報
2024/08/08(木) 開催

2025/03/31(月) 開催
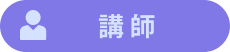
2025/03/31(月) 開催
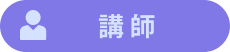
2025/03/31(月) 開催

2024/08/08(木) 開催

2025/03/31(月) 開催
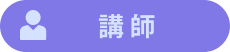
2025/03/31(月) 開催